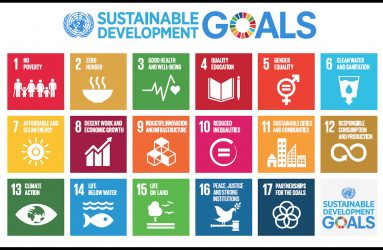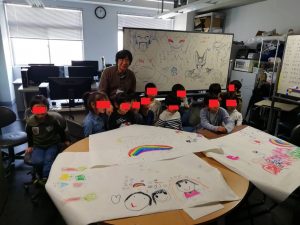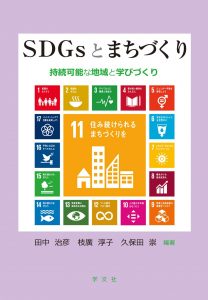国関係
1991年~2004年に環境庁環境研修センターの地域環境研修や環境基本計画研修などの講師を担当。2000年~2006年および2011年には総務省市町村アカデミーの地球環境研修講師、2001年には市町村国際文化研修所の温暖化対策研修講師、2014年以降総務省自治大学校の研修講師(環境政策)を毎年3回以上勤める。また、1998年度、2004~2005年度には環境省の環境基本計画の目標見直し検討会、2002年度、2005~2006年度には地球温暖化防止地域推進計画策定ガイドラインの委員、2007年度には地球温暖化影響・適応研究委員会国民生活・都市生活分野ワーキンググループ副査、2008年度~2009年度には「環境保全の人づくり・地域づくりの推進」に係る指標の充実化に向けた検討委員会の委員を務める。2005~2006年には内閣府先駆的省資源・省エネルギー実践活動等推進事業に関する審査会委員、2010年度~2011年度環境省第4次環境基本計画における指標に関する検討委員会委員、2011年度環境省J-VER制度運営委員会委員、2011年度 環境省エコアクション21業種別ガイドライン(大学等)検討分科会委員も勤める。
自治体関係
豊中市、草加市、藤枝市、富士市、茅野市、狛江市、大野市、島田市、鶴ヶ島市、渋川市、三島市、高島市、大東市、神奈川県、東松山市、横浜市などで環境政策や環境基本計画についての研修講師、京都府、仙台市、古河市、新旭町、内子町、八幡市、綾町、士幌町、沼津市、八王子市、伊丹市、高島市、交野市、遊佐町、福生市、吹田市などで環境マネジメントシステムに関する研修講師を勤め、大阪府、静岡県、東京都、宮城県、京都市などで環境指標の研修講師やアドバイザー、埼玉県、草加市、我孫子市、美濃加茂市、日野市、豊中市、綾町、士幌町、国立市、特別区職員研修所などで地球温暖化対策やライフスタイルに関する研修講師を勤める。また2002年京都市環境管理計画策定委員、2006年度~2007年度には神奈川県ローカルアジェンダ評価委員会委員、2006年度~2009年度には埼玉県環境マネジメントシステム外部評価委員会委員長、2007年度より現在まで東京都オリンピック環境アセスメント評価委員会委員、2009年度には特別区協議会のカーボン・オフセット委員会委員、2010年度さいたま市温暖化対策実行計画区域施策編策定委員、2011年度埼玉県彩の国クールスポット100選選定委員などを務める。
外郭団体関係
日本環境衛生センター、環境アセスメントセンター、環境情報科学センター、日本経営協会、地球環境と資源エネルギーを大切にする国民運動全国会議、国際環境技術移転センター、JICAなどの主催するセミナーにおいて、環境計画、環境指標、環境マネジメント、エコロジカルライフスタイルに関する講演を行う。また2005年度には(社)産業環境管理協会の定量的環境情報ラベルである「エコリーフ」のレビューパネル委員を勤める。
市民セクター
かわごえ環境ネット(市民と行政のパートナーシップ組織)理事3期勤めたのをはじめ、多くの環境NGO、NPOの活動に関わる。気候ネットワーク、かながわNPOセンター、東京マイコープ、かながわアジェンダ推進センター、とよなか市民環境会議アジェンダ21などの講座の講師も歴任。
講演や委員就任などを依頼したいとお考えの皆様へ
1)単発の研修・講演、シンポジウムのパネリストなどにつきましては、日程の都合がつく限り、すべて喜んでお受けさせていただいております。
2)環境政策や市民協働に関わる委員会の委員、連続ものの研修などは、環境自治体会議の会員自治体もしくは地元自治体に限りましてお受けさせていただいております。(国および都道府県主体のものは、この限りではありません)
3)条例等で定められた審議会につきましては、中口はその効果や必要性に疑問を持っております。年数回、1回あたり2時間程度の会合で政策の点検・評価・提言を行うには限界があります。政策・活動を立案・実践する側に立って汗をかくのが自分の立ち位置と考えていることから、審議会の委員は環境自治体会議の会員や懇意にしている自治体であっても、すべてお断りしています。